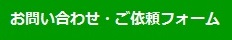
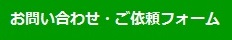
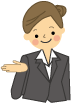
| 永住権取得のメリット |
|---|
|
原則10年在留に関する特例 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子と特別養子の場合は1年以上本邦に継続して在留していること 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の資格を取得した場合、通常は初年度「1年」1回目の更新「3年」2回目の更 新で「3年」の在留期間が許可されますので、この3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時に永住許可の申請が可 能です。 (2)「定住者」(インドシナ定住難民を含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること (入国管理局の「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい) ※「継続して」とは、在留資格が途切れることなく続いていることで、再入国の許可を得ずに出国したり、再入国の許可を得て出国した場合であっても、海外滞在中に再入国の許可期限が到来してしまったり、あるいは在留期限が過ぎてしまったような場合は、その時点で一度在留資格が途切れてしまいます。従って、「継続して」いるとは言えませんので、ご注意下さい。 |
| みなし再入国許可について |
| 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。 みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。 具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックして,入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。 みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。従って在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。 出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。(特別永住者の方は,再入国できる期間は2年間) |
| 帰化の一般的条件(国籍法第5条) |
|---|
帰化には、普通帰化、簡易帰化(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で日本と特別な関係を有する外国人で、一定の者については、帰化の条件が一部緩和される)、大帰化(日本に特別な功労がある外国人について、法務大臣が一般の帰化条件にかかわらず、国会の承認を得て許可するもの)がありますが、ここでは、普通帰化の条件について記載します。 |
| 業務 | 入管手数料 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(入国許可) | 不要 | 77,000円~99,000円 |
| 在留期間更新許可申請(ビザの更新) | 5,500円(オンライン申請) | 44,000円~77,000円 |
| 在留資格変更許可申請(ビザの変更) | 5,500円(オンライン申請) | 77,000円~99,000円 |
| 永住許可申請(日本での永住権取得) | 10,000円 | 88,000円~110,000円 |
| 再入国許可申請 | 3,500円(1回)(オンライン申請) 6,500円(複数回)(オンライン申請) |
11,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 不要 | 22,000円~44,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 1,600円(オンライン申請) | 22,000円~44,000円 |
| 在留資格取得許可申請 | 不要 | 22,000円 |
| 帰化申請(日本国籍取得) | 不要 | 165,000円~275,000円 |
| 理由書のみ作成 | - | 16,500円 |